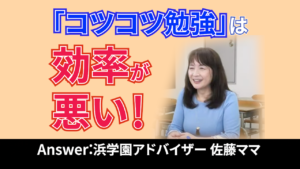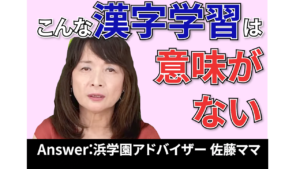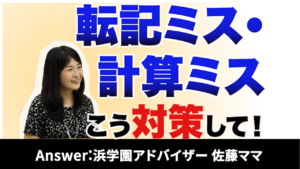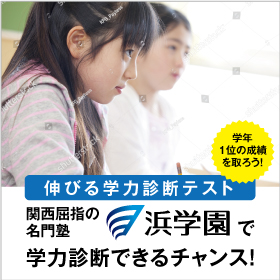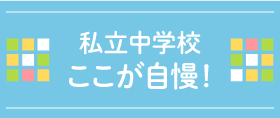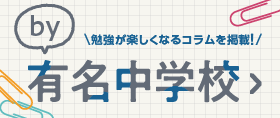その言い方では子どもの心を閉ざしてしまっているかも?
ケアレスミスが多い、テストが悪かった、まじめに机に向かわない……受験生の子どもをもっていると、こういうときについ、厳しく叱りすぎてしまうことがあります。子どもの「これから」を真剣に考えるからこそ、「今しかない勉強時間をしっかり使ってほしい!」というのが親の心理でしょう。
しかし、子どもは「叱りに来たな」と思うと、心を閉ざしてしまいます。心のドアをぴしゃっと閉めてしまうようなイメージで、叱られている内容もまったく頭に入らないのです。
受験勉強に関しても「やらされているもの」というイメージを強めていき、主体的に、前向きに取り組まなくなります。こうなると、お互いにとってストレスです。子どものためを思って言っているはずなのに、子どもとの距離が空いてしまうことになるのです。
こういった状況を防ぐためには、なるべく「物事をプラスに捉える」ことを意識するようにしましょう。
完璧な子どもはどこにもいないのです。難関校に合格した子どもにだって、苦手な分野や悪かったテストはあったはずです。頭ごなしに叱るのは避けて、何かひとつでもよい点を見つけて褒めていくのです。
当たり前のことを褒める
大人にも言えることですが、「できることをやっても、“当たり前だから”といって褒めてもらえない」のは寂しいものです。たとえば宿題をしっかりやっているとか、ケアレスミスをしなかったとか、そういった「当たり前」と見なされがちな点もなるべく拾って褒めるようにしましょう。
このとき、かならず「口に出して言ってあげる」ことが大事です。「えらいな、頑張っているな」と思っていても、それを口に出して言わなければ、子どもには伝わりません。
褒め言葉を口に出さず、注意だけしていると、子どもにとっては親の言葉が「マイナスの声かけ」ばかりになってしまうのです。
逆にマイナスの声かけに関しては、何度も繰り返して言うのは逆効果。子どもが繰り返し、同じような行動をしているのならば、「注意する点を紙に書いて部屋に貼る」などの工夫をし、口にする回数を減らしていきましょう。
プラスの言葉があふれる家庭なら、きっと家族で一丸となって受験に取り組めるはず。そのためにもぜひ「プラス思考」を意識してみてください。
進学教室浜学園