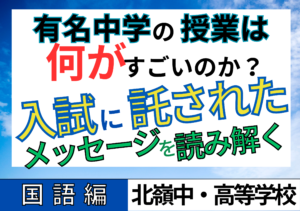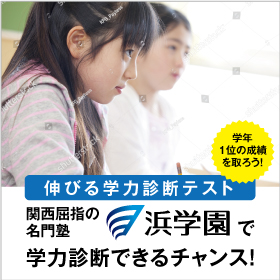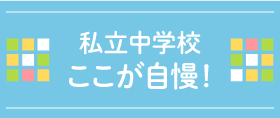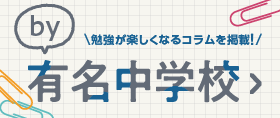一文字の差

執筆:北嶺中学校 国語科教諭 村瀬 洸平
今回は、主語を表す助詞として頻繁に用いられる「が」と「は」について説明します。どちらの助詞も同じ役割と認識している人が多いと思いますが、実はこの二つの助詞には明確な違いがあります。この違いを『桃太郎』を例文にしながら確認していきます。
A:むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。
どちらも同じ役割をもつ言葉なら、「が」を「は」に入れ替えても同じ意味になるはずです。入れ替えた文を見てみましょう。
B:むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんは住んでいました。
Bも文として成立しているように見えますが、少し違和感がありませんか?この違和感を解決するには、どちらの例文も物語の「冒頭」だということに注目する必要があります。読者にとって「おじいさんとおばあさん」は、物語でまだ登場していない、知らない情報です。そういった知らない情報が初めて与えられるとき、日本語では「が」を用いるのです。こういった「が」の性質を、学問の世界で「未知(知らないこと)」と呼びます。それでは、続きを見てみましょう。
C:おじいさんは山へ柴刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。
この文でも、「は」を「が」に入れ替えてみます。
D:おじいさんが山へ柴刈りに、おばあさんが川へ洗濯に行きました。
やはり、物語の「続き」として見ると、Dの文に違和感があります。今回の場合、読者はAの文で既に「おじいさんとおばあさん」という情報を既に知っているのに「未知(知らないこと)」を表す「が」を使っているため、違和感があるのだと考えられます。一方、Cの文が物語の「続き」として成立するのは、「は」には「既知(既に知っていること)」という性質があるからです。
このように、一文では日本語として成立していても、文が増えると違和感をもつケースがあります。その他にも、以下のようなケースがあります。子どもが書く文でよく見られるものです。
E:姉は帰ってきたら、ピアノの練習をする。
F:姉が帰ってきたら、ピアノの練習をする。
EとFは「が」と「は」を入れ替えただけですが、ピアノの練習をするのは誰か、という観点で文を見ると、それぞれ違うことに気づきませんか?Eは「姉」なのに対し、Fは「誰だかわからない」になりそうです。
これは、「は」という助詞の「直後にも、さらに後ろの言葉にもかかる」という性質が関係しています。「は」とセットになっている「姉」という情報が「帰ってくる」と「練習をする」の二つにかかっているのです。
一方、「が」という助詞は「直後にだけかかる」という性質を持っているため、「が」とセットになっている「姉」という情報が「帰ってくる」にだけかかるのです。その結果、「練習をする」のは誰なのかがわからないまま文が終わっています。
このように、たった一文字入れ替えただけでも読んだ人に与える印象(A〜D)や、文の内容(E、F)が変わってしまいます。よく使う言葉だからこそ、使った後にはよく見直して、違和感がないか確認する必要があります。もし違和感の正体がわからないときは、書いた文を先生に見てもらうと良いでしょう。読んでもらう人に伝わりやすい文の形はないか、何度も修正することで文を書く力が高まります。書いたものを見られるのは恥ずかしい、という気持ちもあると思いますが、それを乗り越え、どんどん自分の文章力を高めていきましょう。
進学教室浜学園