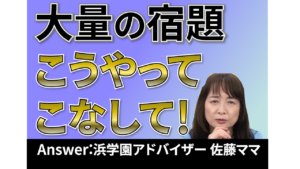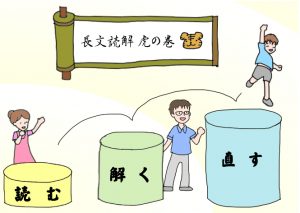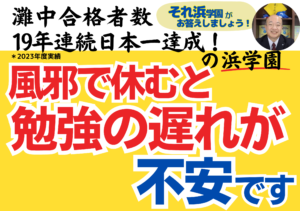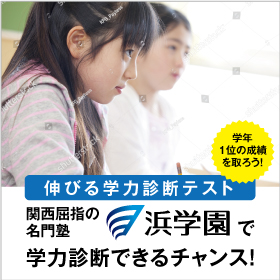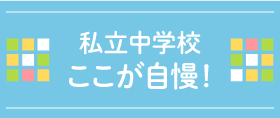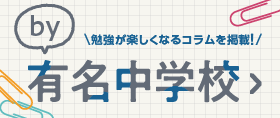算数のノートは「マス目ノート」がGood!点数を左右する図の描き方

学年が上がり、問題の内容が複雑になればなるほど、「図を描いて整理する」力が必要になってきます。
とはいえ、誰しも最初は描き方のコツがわからないもの。
今回はそんな「図」、そして「ノートづくり」に関して、おすすめしたい3つのポイントをまとめました。
1. 図はフリーハンドで描く!
きれいな図を描こうとして、ものさしを使う子がいます。ある意味、几帳面でよいことなのですが、受験勉強では効率も重要。
1本1本、線を引くたびにものさしを動かすのでは、時間と労力をロスしてしまうことになります。
図は必ず、フリーハンドで描かせるようにしましょう。
ただし、これは「デタラメに書いてもよい」ということではありません。
長さの比や角度があまりにもデタラメなのでは、図を描いて整理した意味がなくなってしまいます。
はじめは時間がかかってもよいので、ある程度はフリーハンドでも正確な図を描けるように練習させましょう。
2. 使うノートは必ず「マス目」に!
用途に合わせて、さまざまなレパートリーが展開されている学習用ノート。便利になったのはいいのですが、「あまりに種類が多すぎて、どれを選べばいいのか分からない」という意見もあるようです。
ここでおすすめしたいのは、ズバリ「マス目ノート」。
必要な長さを毎回ものさしで測っていては、効率が下がってしまいます。
あらかじめドットが打ってあるノートやマス目ノートを使うことで、ものさしを使う必要がなくなり、スピードアップにつながるのです。
3. カラーペンを使いすぎない!ペンは「3色」で充分
女の子に多いケースですが、見た目をきれいに飾ろうとして、いろいろな種類のカラーペンを使ってしまう子がいます。赤、青、黄色、緑、ピンク、紫、キラキラペン……と、筆箱の中身がカラーペンでいっぱいになっている子供も珍しくありません。
カラフルなノートは一見、完成度が高く見えるのですが、実はこれも効率ダウンのもと。
図は本来、わかりやすく整理することで問題を解く速度を上げるためのものです。
ノートの装飾に気を取られ、貴重な時間をロスしてしまうのでは、本来の目的とは正反対の方向に進んでいることになります。
装飾はほどほどにして、効率を重視したノート作りを目指しましょう。
とはいえ、まったく色が使われていないノートも見返したときにわかりにくいもの。
重要な部分を強調するために、「赤」を使用するのはOKです。
だんだんと情報が複雑になり、赤だけでは対応しきれなくなった場合には、「青」や「緑」を必要に応じて増やしましょう。
ただし増やしてもいいのは「赤」「青」「緑」の最大3色まで。
事務用品として販売されている「3色ペン」を目安としてください。
以上、今回は作図を中心に、ノートづくりで気をつけたいことをまとめました。
効率を重視した上で情報をわかりやすく整理する力は、受験だけでなく、すべての局面で必要になってくる能力です。
慣れるまで時間がかかるかもしれませんが、根気よく練習させてみてください。
進学教室浜学園